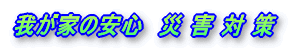 万が一の時、頼れるのは、自治体のサポート力と自分自身の災害に対する心構え、備えなのです。 このページは、首都直下地震の可能性についてご紹介しています。 |
 |
| 首都直下地震の可能性について |
|
M E N U ■地震時の心得10か条 ■地震の前兆現象について ■被害者からの教訓 ■地震後の暮らしの保障について ■震度とマグニチュードについて ■地震に弱い場所(1)軟弱地盤 ■地震に弱い場所(2)活断層上 ■東京直下地震の時−被災者は ■住宅が壊れた場合のローン ■地震保険、損害保険、税金還付 ■日本の安全神話は崩壊か ■地震にあう場所ごとの対処法 ■首都直下型はM7〜8 【災害対策グッズ】 |
首都地域では、大正12年(1923年)に関東地震(関東大震災)が発生し,未曾有の大災害を引き起こしました。関東地震の地震のタイプは、いわゆる「海溝型」の地震であり、その規模はマグニチュード8クラスという巨大地震でした。 首都地域では、このような海溝型の巨大地震は200〜300年間隔で発生するものと考えられています。現在は、1923年の関東地震から80年余りが経過したところであり、次のマグニチュード8クラスの地震が発生するのは、今後100年から200年程度先と考えられています。 一方、次の海溝型の地震に先立って、プレートの沈み込みによって蓄積された歪みの一部がいくつかのマグニチュード7クラスの地震として放出される可能性が高い。 次の海溝型の地震が発生するまでの間にマグニチュード7クラスの「首都直下地震」が数回発生することが予想されており、その切迫性が指摘されています。 ライフライン被害については、18時・風速15m/sのケースでは、発災後一日目で断水人口約1,100万人(約450万軒)、停電軒数約160万軒、ガス供給停止軒数約120万軒と想定されています。 避難者数については、一日後の避難者数を最大で約700万人。このうち親戚、知人宅に避難する人等を除いて実際に避難所で生活する人は、最大で約460万人と想定しています。 阪神・淡路大震災のピークで約30万人、新潟県中越地震で約10万人だったことと比較すると、桁違いに多くの避難者が発生します。 ■2007年11月1日発表 国の中央防災会議の専門調査会がまとめた地震の被害想定
|
| このページのトップにもどる |
| Copyright (C) All Rights Reserved 災害避難グッズ |