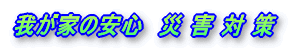 万が一の時、頼れるのは、自治体のサポート力と自分自身の災害に対する心構え、備えなのです。 このページは、地震の大きさを表す言葉、震度とマグニチュードの違いについてご紹介しています。 |
 |
| 地震の大きさ−震度とマグニチュードの違いについて |
|
M E N U ■地震時の心得10か条 ■地震の前兆現象について ■被害者からの教訓 ■地震後の暮らしの保障について ■震度とマグニチュードについて ■地震に弱い場所(1)軟弱地盤 ■地震に弱い場所(2)活断層上 ■東京直下地震の時−被災者は ■住宅が壊れた場合のローン ■地震保険、損害保険、税金還付 ■日本の安全神話は崩壊か ■地震にあう場所ごとの対処法 ■首都直下型はM7〜8 【災害対策グッズ】 |
地震があった時、テレビやラジオのニュースで震度○とかマグニチュード○○という言葉を聞きます。ここでは震度とマグニチュードのちがいを説明します。 「震度」はある地点での揺れを意味します。「マグニチュード」は地震そのもののエネルギーを示します。テレビなど では「地震の規模を示す、、、」と言っています。 マグニチュードは、地震が岩石の破壊によって発生するという認識がなかった頃の尺度です。必ずしも現実的な表現ではありません。マグニチュードの大きさと震源の破壊の規模は比例するので、震源から放出されるエネルギーの大きさを表す相対尺度といえます。 震度は、各地点の揺れの強さを人体に感じた程度や周囲の揺れ方、被害の状況などによって区分した地震の揺れの強さを表す尺度のことをいいます。震度は、ひとつの地震でも、震源からの距離や観測点の状況などによって違ってきます。軟弱地盤の場所で起きた地震の時ほど数字が大きくなります。 言い方をかえれば1回の地震で、マグニチュードは1つしかありませんが、震度はそれぞれに感じた大きさなので、観測した人の数、計測震度計の数だけあるといえそうです。この計測震度計は全国で600ヶ所設置されています。 震度の強弱を表す階級は、各国によってまちまちです。建築様式や生活様式が違うので、世界共通にはいたっていません。 日本では、気象庁が出している気象庁震度階級の震度0から震度7が広く使われています。報道などの発表でよく耳にしたり目にしたり する言葉で震度5弱とか震度5強とかあります。震度5と6の場合は、震度弱と震度強があり実質的には10段階で使っています。この10段階が使われだしたのは、阪神淡路大震災以降のことです。 明石海峡の海底が震源の阪神大震災の場合の分類は、マグニチュード7.2(直下型地震ではやや大型)、神戸市の数カ所で震度7(激震)を記録しました。震度7は、この阪神淡路大震災で始めて使われた震度です。 ちなみに関東大地震(1923.9.1)は、M7.9で震度6の烈震。北海道東沖地震(1994.10.4)も、M7.9でした。 新潟中越沖地震(2007.7.16)は、M6.8で、新潟県長岡市、柏崎市、刈羽村、長野県飯綱町は震度6強でした。 この震度0〜7というのは使っているのは日本だけ、日本しか通用しません。海外では1〜12までの12段階を使うのが主流となっています。代表的なものは、1931年に作られた「改正メルカリ震度階」、通称MM震度階です。このMM震度階を用いた海外の地震報道で震度7といっても、日本ではせいぜい震度4の中震程度なのです。 マグニチュードも絶対的な数字ではありません。 20世紀最大の地震といわれる1960年に起きたチリ地震はM8.3と記録されています。この時は地球の自転が狂ったし、地球が何日も釣り鐘のように震え続けたと記録されています。津波は太平洋を横断して、23時間後に日本に届きました。日本だけでも140人もの死者と行方不明者をだしました。 このM8.3が日本で起こった記録があります。1933年の三陸沖地震です。とても同じM8.3に思えません。その後の研究でチリ地震が日本の三陸沖地震より桁違いに大きかったことがわかりました。 マグニチュードを決める方法は、震源から伝わってきて地震計に記録された地震の波の強さから震源での地震の大きさを計算しています。この問題点は、地震の波が地殻の種類や硬度、あるいは深さなどによって異なる値をだしてしまうことです。ひとつの物差しでは測れないということです。 ■地震の震度(気象庁震度階級)
■マグニチュードの区分
マグニチュードが1増えるとエネルギーは約30倍になる。 M6を1とすると、M7は約30倍。M8になると、約1000倍になる。 ちなみに、北海道東方沖地震(1994年10月4日)はM8.2でした。兵庫県南部地震はM7.2です。エネルギーとしては、30倍もの開きがあります。これを見ても地震の大きさと被害の大きさは比例はしません。震源地の地盤構造と建物構造だということがわかります。 北海道は雪対策の為に軽量のトタン屋根が多く、兵庫県の場合は、かわら屋根の一般住宅と建物上部の重量に耐えられなかったコンクリート建物が被害を大きくしました。 気象庁では、全国129の観測所でM3以上の地震について観測しています。微小地震は発表されていません。 ■2007年11月1日発表 国の中央防災会議の専門調査会がまとめた地震の被害想定
|
| このページのトップにもどる |
| Copyright (C) All Rights Reserved 災害避難グッズ |