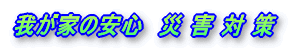 万が一の時、頼れるのは、自治体のサポート力と自分自身の災害に対する心構え、備えなのです。 このページは、地震に弱い場所と軟弱地盤地域についてご紹介しています。 |
 |
| 地震の地震に弱い場所(1)軟弱地盤地域 |
|
M E N U ■地震時の心得10か条 ■地震の前兆現象について ■被害者からの教訓 ■地震後の暮らしの保障について ■震度とマグニチュードについて ■地震に弱い場所(1)軟弱地盤 ■地震に弱い場所(2)活断層上 ■東京直下地震の時−被災者は ■住宅が壊れた場合のローン ■地震保険、損害保険、税金還付 ■日本の安全神話は崩壊か ■地震にあう場所ごとの対処法 ■首都直下型はM7〜8 【災害対策グッズ】 |
地震に弱い場所、地域があります。 それは一口に言って、住んでいる土地が海水面より低いゼロメートル地域。埋め立て地。海岸地帯でなくても河川沿いの地域。 木造家屋が未収している地域。山すそ、丘陵傾斜地で宅地造成地。このような地域にお住まいの方は地震に弱い場所に住んでいるということを知って下さい。 ゼロメートル地帯にお住まいの方は、大地震に襲われると家屋倒壊、火事、水害の複合被害が予想されます。 軟弱地盤の埋め立て地や河川沿いは、砂が堆積した砂層地盤です。 このような土地は、大きな地震の際に地盤が流動して土地が泥砂化するいわゆる「液状化現象」にみまわれ、家が大破する恐れがあります。 阪神大震災ではポートアイランドでこの現象が起こりました。東京で同様の地震が起こった場合、足立区、葛飾区、江戸川区などで4万棟以上が倒壊すると予想されています。 阪神大震災発生後、地盤と被害地域の関係について調査した方がいます。この調査で明らかになったことは、被害の空白地帯があるということでした。 このときの被害調査地図と1886年の地図と重ねてみたところ、被害の空白地帯は、水田に囲まれた昔の集落や海岸の砂丘部分だったということです。 この被害空白地域は水田にできない固い地盤の土地、場所だったとのことです。この安全地帯周辺の被害が大きかった地域は、その後都市化で水田が住宅地になり、今や昔の面影不明の場所だったということです。 このことでも軟弱地盤の埋め立て地などに建てた住宅はもろいということがわかります。 水田に適した場所は、低地で三角州、扇状地といわれているところです。山麓地帯から流れ出た河川が栄養分を大量に含んだ土砂を長い年月をかけて河口まで運びこみました。 縄文のころからこのような肥沃な土地に集落が栄え、水田も集中してきました。 このような海岸線に暮らし始めた昔の人たちは一体どこに住まいを構えたのでしょうか。 先の明治時代まで集落としてあったのが三角州のや扇状地の中に浮島のように点在する砂堆といわれる場所です。地盤が固い上、水はけもいい場所でした。 この他、被害が集中した地域がありました。異なる地盤の境界線付近や旧河川跡山際の扇状地と河口の三角州の境目です。崩れ落ちた阪急伊丹駅がその典型地です。 駅の北半分は河岸段丘で駅の南側は近年埋め立てられて宅地化された低湿地区域です。伊丹市内の新幹線の路線が被害を受けた場所。三宮、フラワーロードも被害甚大でした。 昭和13年の阪神大水害の被災地も同じ場所でした。 「災害は忘れたところにやってくるのではなく、過去を無視した土地利用が度を超すと、大地がキバをむく」ということでしょうか。 ■2007年11月1日発表 国の中央防災会議の専門調査会がまとめた地震の被害想定
|
| このページのトップにもどる |
| Copyright (C) All Rights Reserved 災害避難グッズ |