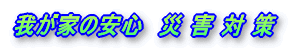 万が一の時、頼れるのは、自治体のサポート力と自分自身の災害に対する心構え、備えなのです。 このページは、地震に備える心得10か条をご紹介しています。 |
 |
| 地震時の心得10か条 |
|
M E N U ■地震時の心得10か条 ■地震の前兆現象について ■被害者からの教訓 ■地震後の暮らしの保障について ■震度とマグニチュードについて ■地震に弱い場所(1)軟弱地盤 ■地震に弱い場所(2)活断層上 ■東京直下地震の時-被災者は ■住宅が壊れた場合のローン ■地震保険、損害保険、税金還付 ■日本の安全神話は崩壊か ■地震にあう場所ごとの対処法 ■首都直下型はM7~8 【災害対策グッズ】 |
① グラッときたら身の安全。 揺れている間はテーブルなどの下に身をふせる。座布団などで頭を保護する。家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止措置を講じておく。 ② すばやい消火。火の始末。 「地震だ、火を消せ!」声を出して、気持ちを落ちつかせる。消火器の準備や風呂の水のくみ置きを毎日しておく。 ③ 窓や戸を開けて、まず出口を確保せよ。 開けたドアは再び閉まらないように物をはさむ。 ④ 落下物あり!あわてて外に飛び出すな。 窓ガラスや看板の落下に要注意。ベランダにはものを置かない。 ⑤ 我が家の安全、隣の安否、互いに声をかけあおう。 離ればなれになった時の連絡方法や集合場所を決めておく。災害時伝言ダイアルの利用方法を覚えておく。 ⑥ 避難の前に電気とガスの安全確認。 絶対に火元にならないこころがけ。 ⑦ 門や塀には近寄るな。 危ない塀は、鉄筋が入っていない。高さが2m以上。薄っぺらい。老朽化。亀裂がある。 ⑧ 室内のガラスの破片に気をつけよ。 素足では絶対歩かない。後かたづけには、厚手の手袋を使用する。寝る時は近くにスリッパを置いておく。 ⑨ 協力し合って救出・応急救護。 ノコギリやスコップなどの器具を備え、救出や応急処置の訓練をしておく。 ⑩ 正しい情報・確かな行動。 携帯ラジオと感電委を常備する。デマや噂に振り回されない。避難先は、事前に歩いて確認しておく。 ○補足 自宅から避難する時は、必ず電気のブレーカーを切る。 これは、停電普及時の「通電火災」を防ぐ為です。倒壊や半倒壊家屋で人が避難したあとの無人家屋から出火が大変多いのです。木造家屋は、燃えやすい薪の山になっています。阪神大震災のあと、神戸消防局が火事の原因を調査したところ電気器具や電源に関連して起こった火災は、44件ありました。電気は、地震の翌日から1週間ほどかけて全域に電気が通じるようになりました。 ■2007年11月1日発表 国の中央防災会議の専門調査会がまとめた地震の被害想定
|
| このページのトップにもどる |
| Copyright (C) All Rights Reserved 災害避難グッズ |